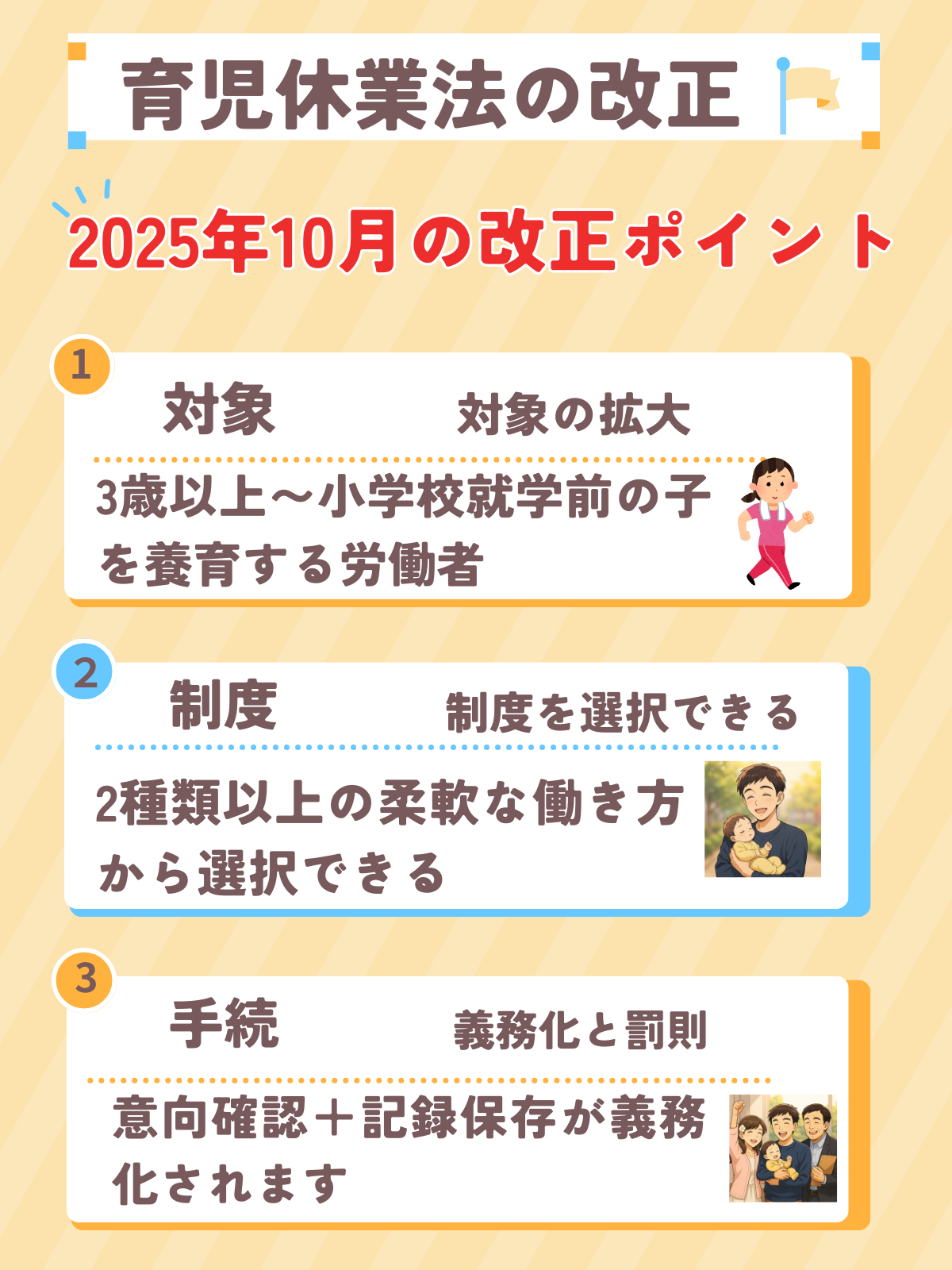就業規則とは?
就業規則は、会社で働く全員が同じ前提で動けるようにする共通ルールです。始業や終業、休憩や休日、賃金の決め方と支払い方法、残業の扱い、遅刻や欠勤時の取り扱い、そして懲戒や退職までの道筋を一冊にまとめます。口頭の「うちの慣習」だけで回していると、人が増えたり担当が代わった瞬間に解釈が食い違い、対応がぶれます。文章で示された規則があれば、誰が読んでも同じ答えにたどり着けます。
就業規則と雇用契約書のちがい
就業規則は、雇用契約書と役割が違います。契約書は一人ひとりとの個別の約束で、入社日や勤務地、賃金額のような個別条件を書きます。就業規則は全員に共通する土台で、時間や休暇、服務、ハラスメント防止などの会社全体の方針を定めます。両者がそろって初めて、個別の約束が全体のルールと矛盾なく運用できます。
周知が必要
もう一つの大事な点は、周知です。規則は作成しただけでは効力が弱く、従業員がいつでも確認できる状態にして初めて意味を持ちます。紙で配る、掲示や社内システムで常時閲覧できるようにするなど、方法を決めて見える化しましょう。外国人が多い職場なら、やさしい日本語の要約や図解を添えるだけで理解が進みます。
小さな会社ほど、就業規則は効きます。数人のうちは口約束で済んでも、採用が続くと必ず例外が生まれます。残業代の計算基準、年休の与え方、私物持ち込みや副業の扱い、テレワーク時の勤怠記録など、先に書けば迷いが減り、判断も早くなります。経営者の説明負担が減り、現場は同じ物差しで動けます。
また、就業規則は会社の実態に合わせて作ることが肝心です。ネットの雛形をそのまま使うと、実際の勤務シフトや手当の設計、評価や異動の運用と噛み合わず、紛争時にかえって不利になります。自社の働き方を棚卸しし、現場で起きがちな場面を想定して、言葉を具体的に整えましょう。固定残業なら対象業務と時間数、超過精算の方法まで、懲戒なら手続と弁明の機会まで、年休なら付与基準と時季変更の考え方まで、読み手が迷わない書き方にしましょう。
就業規則は随時改定するもの
最後に、規則は作って終わりではありません。法改正や組織変更、働き方の変化に合わせて見直しを重ねることで、現場に根づいた“生きたルール”になります。見直しのたびに説明資料を配り、質問を集め、改定の意図を丁寧に伝える。その積み重ねが信頼を育てます。就業規則は、リスクを避けるための消極的な文書ではなく、採用や定着を底上げする運用ツールです。だからこそ、いまの規模でも、これから大きくなる会社でも、最初の一歩として整えておきましょう。
従業員が1人以上いたら就業規則を作りましょう
従業員が1人でもいる会社なら、法的義務を超え、就業規則の整備は経営の安心と法的安全のために不可欠です。労働基準法第89条により、常時10人以上の事業場では就業規則の作成と届出が義務づけられていますが、実際には従業員が10人未満でも「書いておくべき」重要な理由があります。
まず、トラブル防止です。就業規則があれば、勤務時間、残業、休暇、懲戒などの基本ルールを誰にもわかる形で示せ、「口頭ルール」の曖昧さによる争いを防ぎます。特に法的な立場が曖昧な小規模企業では、いざというときにルールが“盾”になりえます。熊本の社労士事務所も「一人からでも、就業規則の整備を検討すべき」と地域の実例を通じて提案しており、口頭説明だけでは説明責任を果たせず、対応に苦慮したケースがあるとしています。
次に、助成金や外部支援を受ける際の条件にもなります。特に働き方改革関連の助成金では就業規則が審査項目として使われるケースが増えており、この整備によって無駄な機会損失を避けられます。
さらに、従業員に安心感を与える効果も大きいです。明文化されたルールは公平である証になり、働く側の不安を軽減し、定着率向上につながります。逆に規則がないと、会社に「未整備」「無秩序な環境」としての印象を与える原因ともなり、採用や評価においてマイナスです。
残業指示に関する具体例も見逃せません。36協定の締結・届出だけでは、時間外労働が法的に受け入れられる「最低限の枠」としかなりませんが、就業規則に「必要に応じて残業を命じる」という根拠条項が加わることで、業務命令として正式に認められる体制が整います。
最後に、子会社・支店などの複数事業場がある場合や労働形態が多様化している場合は、就業規則があると「業務の一貫性」と「法的対応力」が強化されます。文書化された内部ルールがあることで、従業員や関係者への説明もスムーズになり、信頼性が高まります。
「就業規則や労務管理のご相談はこちら」→ https://legalcheck.jp/ask/
【次のブログ記事のご案内】:
就業規則入門② 就業規則は10人未満でも必要?作成義務と改定・不利益変更の注意点
https://legalcheck.jp/2025/09/05/rulubook2/
概要
就業規則の周知義務と届出義務
📘 就業規則は周知してこそ効力がある
労基法106条では、規則を掲示・配布・イントラなどで「労働者がいつでも見られる状態」にすることが求められます。
机に眠らせた規則は存在しても無効。効力を発揮するには従業員への周知が必須です。
✅ 周知の具体的方法
・社内掲示板に掲示
・冊子やPDFで配布
・イントラネットやクラウドで公開
どの方法でも構いませんが、「実際に従業員が知り得る状況」にあることが大切です。
📘 労基法89条による届出義務
常時10人以上の事業場では、就業規則を作成して労基署に届け出る義務があります。
届出を怠ると、調査時に是正勧告の対象となり「労務管理が甘い」と評価されます。
✅ 届出と周知はセットで考える
届出を済ませても、周知しなければ従業員に効力が及びません。
逆に周知だけして届出を怠れば、行政から指摘を受けます。
どちらか片方ではなく「届出+周知」の両方を実践することが会社を守ります。
🔑 実務でのポイント
・周知した証拠を残す(配布記録、イントラ掲載ログなど)
・届出は労基署に2部提出し、1部は会社で保管する
・変更時は必ず意見書を添付して届出を行う
👉 就業規則は「作って終わり」ではなく「届け出て、周知して、記録を残す」までが一連の流れです。詳しくはプロフィールの固定リンクからどうぞ!